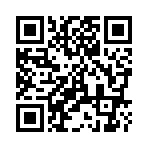2025年05月09日
MAXFANギア交換手順について
新しい予備用のギアが手元にきました、
写真のように本体に一部ふくらみと
ボルトで強化されているようです、
水平位置を白くマークしました。


取替の手順書が付いていましたが、英語です、
写真と挿絵でも理解できますが、
PDFにしてパソコンで翻訳しました。

前回ブログでの販売店のPDFでは、
シャフトを時計回りに回し、全閉し、反時計回りに戻し、
六角ソケットを水平にすると表記されていました、
今回添付の手順書を翻訳すると時計回りの表現は同じですが、
全開するとなっています、
販売店のPDFはギアを下から見た時計回りの表現、
今回の手順書は上から見た時計回りの表現の違いのようです。
今回の手順書、全開にして水平に戻すが正しいと思いますので、
手順書を翻訳した内容を記載しますので参考にしてください。

A
蓋を開いた位置まで上げます。モデルを手動で開くときは、オペレーターアセンブリを交換する前にノブを取り外す必要があります。ノブを取り外すには、ロックノブをシャフトに固定しているネジとワッシャーを取り外します。注意: 自動開口モデルでは、ノブを取り外す必要はありません。
B
MaxxFanを開いた状態で、2本のリアヒンジネジを取り外します。

C
上記のように、レインシールドが下に振れるのを待ちます。
D
リフターアームを広げて、リフターアームを金属ブラケットから外します。プラスチックブッシングは、再取り付けのために保存してください。

E
蓋は全開で、蓋を持ち上げるオペレーターアセンブリ機構に簡単にアクセスできます。
F
リフターアームレールの一端を所定の位置に固定しているプラスチックブラケットを取り外します。プラスチックブラケットは、2本のネジでMaxxFanベースに取り付けられています。これらのネジとプラスチックブラケットを取り外します。すべてのネジ、プラスチックブラケット、およびプラスチックブッシングは、再取り付けのために保管してください。

G
リフターアームに引っ掛けられているスプリングサポートを外します。リフターアームレールをオペレーターアセンブリから引き出して、リフターアームアセンブリをリフティングメカニズムから取り外します。
H
スプリング機構を所定の位置に固定しているナット、ボルト、ワッシャーを取り外します。スプリングメカニズムとすべてのナット、ボルト、ワッシャーは、スプリングを新しいオペレーターアセンブリに再取り付けするために保存してください。
I
オペレーターアセンブリは、2本のネジと2本のスターワッシャーでMaxxFanベースに取り付けられています。ネジとスターワッシャーを取り外します。すべてのネジとワッシャーは、再取り付けのために保管してください。オペレーターアセンブリをMaxxFanから取り外して破棄します。

J
新しいオペレーターアセンブリを取り付ける前に、シャフトが止まるまで時計回りに回します。これにより、リフト機構が完全に開いた位置になります。
K
シャフトを少し反時計回りに戻し、六角ソケットのフラットをオペレーターアセンブリのフラットと平行になるように位置合わせします。
L
オペレーターアセンブリを上記の位置に置き、オペレーターアセンブリの延長部分をファンの中心に向けて配置します。以前に取り外したネジとスターワッシャーを使用して所定の位置に固定します。

M
図のように、オペレーターアセンブリの延長部分に配置されたスプリングサポートを再度取り付けます。以前に取り外したナット、ボルト、ワッシャーを再利用して、スプリングサポートをオペレーターアセンブリに固定します。
N
リフターアームレールを水平(RVルーフと平行)に配置し、リフターアームレールをオペレーターアセンブリにスライドさせます。上記のように、スプリングサポートをリフターアームの下に引っ掛けます。

O
リフターアームレールの端にあるプラスチックブッシングを組み立て直します。ブッシングが所定の位置に配置されたら、プラスチック製のブラケットをリフターアームにかぶせ、所定の位置にねじ込みます。
P
必要に応じて蓋を閉じて、リフターアームを蓋の金属ブラケットに組み立てます。リフターアームポストを蓋の金属ブラケットに挿入する前に、プラスチックブッシングが所定の位置にあることを確認してください。

P
レインシールドを持ち上げ、貴重な取り外しをした2本のネジを使用して、レインシールドアセンブリを蓋に再度組み立てます。
Q
ノブを取り外した場合は、再度組み立てます。これで、オペレーターアセンブリの交換は完了です。MaxxFanの蓋を上下させて、正しく動作していることを確認します。
写真のように本体に一部ふくらみと
ボルトで強化されているようです、
水平位置を白くマークしました。


取替の手順書が付いていましたが、英語です、
写真と挿絵でも理解できますが、
PDFにしてパソコンで翻訳しました。

前回ブログでの販売店のPDFでは、
シャフトを時計回りに回し、全閉し、反時計回りに戻し、
六角ソケットを水平にすると表記されていました、
今回添付の手順書を翻訳すると時計回りの表現は同じですが、
全開するとなっています、
販売店のPDFはギアを下から見た時計回りの表現、
今回の手順書は上から見た時計回りの表現の違いのようです。
今回の手順書、全開にして水平に戻すが正しいと思いますので、
手順書を翻訳した内容を記載しますので参考にしてください。

A
蓋を開いた位置まで上げます。モデルを手動で開くときは、オペレーターアセンブリを交換する前にノブを取り外す必要があります。ノブを取り外すには、ロックノブをシャフトに固定しているネジとワッシャーを取り外します。注意: 自動開口モデルでは、ノブを取り外す必要はありません。
B
MaxxFanを開いた状態で、2本のリアヒンジネジを取り外します。

C
上記のように、レインシールドが下に振れるのを待ちます。
D
リフターアームを広げて、リフターアームを金属ブラケットから外します。プラスチックブッシングは、再取り付けのために保存してください。

E
蓋は全開で、蓋を持ち上げるオペレーターアセンブリ機構に簡単にアクセスできます。
F
リフターアームレールの一端を所定の位置に固定しているプラスチックブラケットを取り外します。プラスチックブラケットは、2本のネジでMaxxFanベースに取り付けられています。これらのネジとプラスチックブラケットを取り外します。すべてのネジ、プラスチックブラケット、およびプラスチックブッシングは、再取り付けのために保管してください。

G
リフターアームに引っ掛けられているスプリングサポートを外します。リフターアームレールをオペレーターアセンブリから引き出して、リフターアームアセンブリをリフティングメカニズムから取り外します。
H
スプリング機構を所定の位置に固定しているナット、ボルト、ワッシャーを取り外します。スプリングメカニズムとすべてのナット、ボルト、ワッシャーは、スプリングを新しいオペレーターアセンブリに再取り付けするために保存してください。
I
オペレーターアセンブリは、2本のネジと2本のスターワッシャーでMaxxFanベースに取り付けられています。ネジとスターワッシャーを取り外します。すべてのネジとワッシャーは、再取り付けのために保管してください。オペレーターアセンブリをMaxxFanから取り外して破棄します。

J
新しいオペレーターアセンブリを取り付ける前に、シャフトが止まるまで時計回りに回します。これにより、リフト機構が完全に開いた位置になります。
K
シャフトを少し反時計回りに戻し、六角ソケットのフラットをオペレーターアセンブリのフラットと平行になるように位置合わせします。
L
オペレーターアセンブリを上記の位置に置き、オペレーターアセンブリの延長部分をファンの中心に向けて配置します。以前に取り外したネジとスターワッシャーを使用して所定の位置に固定します。

M
図のように、オペレーターアセンブリの延長部分に配置されたスプリングサポートを再度取り付けます。以前に取り外したナット、ボルト、ワッシャーを再利用して、スプリングサポートをオペレーターアセンブリに固定します。
N
リフターアームレールを水平(RVルーフと平行)に配置し、リフターアームレールをオペレーターアセンブリにスライドさせます。上記のように、スプリングサポートをリフターアームの下に引っ掛けます。

O
リフターアームレールの端にあるプラスチックブッシングを組み立て直します。ブッシングが所定の位置に配置されたら、プラスチック製のブラケットをリフターアームにかぶせ、所定の位置にねじ込みます。
P
必要に応じて蓋を閉じて、リフターアームを蓋の金属ブラケットに組み立てます。リフターアームポストを蓋の金属ブラケットに挿入する前に、プラスチックブッシングが所定の位置にあることを確認してください。

P
レインシールドを持ち上げ、貴重な取り外しをした2本のネジを使用して、レインシールドアセンブリを蓋に再度組み立てます。
Q
ノブを取り外した場合は、再度組み立てます。これで、オペレーターアセンブリの交換は完了です。MaxxFanの蓋を上下させて、正しく動作していることを確認します。
2025年05月03日
MAXFANギア破損交換
昨年の9月に後部MAXFANギアが破損しました、
今回もまったく同じように強風で前部ギアが破損しました。
今回も仮処置をして帰宅しました。

破損した状態
ギア内部の摩耗ではなく、
本体が粉々に割れてしまっています、



破損したギアは2個ともコーキングした時、
予備に購入したギアに取替したものです、
おそらく本体の強度不足でしょう、

後部と同様、元々ついていたギアに今回も交換します、

ギアの交換、アームの取り付け方法について
下記、販売店のPDFに手順が記載されていました。
https://rv-toyo.jp/products/1266/
ノブを時計回しに全閉に止まるまで回し、

六角の辺が水平になるまで少し戻す

この状態でアームを水平になるよう取り付け固定する。

実は、いろいろなブログを拝見すると
これとは逆に全開に止まるまで回して、
水平に戻し、アーム取り付ける方法もあるようです、
どちらが良いか分かりませんが、
今回マーキングして前部後部とも両方やってみました。
結果は、前部MAXFANギアは同じ位置になりました。


後部ギアは1つ六角の位置がずれていました、
今まであまり使っていなかった摩耗の少ない
ギアのかみ合わせになると思います。



後部はこの状態で様子を見ます。
予備のギアがなくなったので購入手続きをしました。
連休明けになるようです、
外観を見ると、シャフトのまわる部分が膨らみ、
ボルトで本体を固定しているので補強強化しているようです。
写真はコーキング時取り替えたギア

https://www.campingcar-partscenter.jp/shopdetail/000000006134/
今回壊れたとき、予備のギアを持っていましたが、
バロンの屋根に昇ることができず、内部で仮処置をしました。
屋根に昇れればその場で改修できたのにと思い、
ラダーの取り付けがない我が家では、
伸縮はしご(3.2m)を購入積載することにしました。
購入してみると重量は8kg、結構な大きさです。

車体にあたる部分は、タオルで養生、
実際に昇ってみました。
まだ2段余裕があります。



積載場所はベット下収納庫です、高さが足りず横置き、
マジックバンドで固定しました。
長距離、長期間のみ積載しようと思います。




今回もまったく同じように強風で前部ギアが破損しました。
今回も仮処置をして帰宅しました。

破損した状態
ギア内部の摩耗ではなく、
本体が粉々に割れてしまっています、



破損したギアは2個ともコーキングした時、
予備に購入したギアに取替したものです、
おそらく本体の強度不足でしょう、

後部と同様、元々ついていたギアに今回も交換します、

ギアの交換、アームの取り付け方法について
下記、販売店のPDFに手順が記載されていました。
https://rv-toyo.jp/products/1266/
ノブを時計回しに全閉に止まるまで回し、

六角の辺が水平になるまで少し戻す

この状態でアームを水平になるよう取り付け固定する。

実は、いろいろなブログを拝見すると
これとは逆に全開に止まるまで回して、
水平に戻し、アーム取り付ける方法もあるようです、
どちらが良いか分かりませんが、
今回マーキングして前部後部とも両方やってみました。
結果は、前部MAXFANギアは同じ位置になりました。


後部ギアは1つ六角の位置がずれていました、
今まであまり使っていなかった摩耗の少ない
ギアのかみ合わせになると思います。



後部はこの状態で様子を見ます。
予備のギアがなくなったので購入手続きをしました。
連休明けになるようです、
外観を見ると、シャフトのまわる部分が膨らみ、
ボルトで本体を固定しているので補強強化しているようです。
写真はコーキング時取り替えたギア

https://www.campingcar-partscenter.jp/shopdetail/000000006134/
今回壊れたとき、予備のギアを持っていましたが、
バロンの屋根に昇ることができず、内部で仮処置をしました。
屋根に昇れればその場で改修できたのにと思い、
ラダーの取り付けがない我が家では、
伸縮はしご(3.2m)を購入積載することにしました。
購入してみると重量は8kg、結構な大きさです。

車体にあたる部分は、タオルで養生、
実際に昇ってみました。
まだ2段余裕があります。



積載場所はベット下収納庫です、高さが足りず横置き、
マジックバンドで固定しました。
長距離、長期間のみ積載しようと思います。




2025年03月21日
オルタネータ他交換
今年に入り、寒い朝エンジンをかけると、
キューキューというような音がするようになりました。
数十秒すると消え、朝のみ、その後音はしません。
おそらく、テンションプーリのゆるみでVベルトから、
または、各プーリからの音と思われます。

対策として、テンションプーリとアイドラプーリのみの
交換しようと思っていましたが、
走行距離11万キロ、サブバッテリーの充電で通常より、
過度に使用していたオルタネータの交換も今回することにしました、
新品は高価なので約半額のリビルト品を使用、
ついでにウォーターポンプも交換です。
今回交換した物
オルタネータ(AL)リビルト品、ウォーターポンプ(WP)、
テンションプーリ(TP)、アイドラプーリ(IP)2個、Vベルト

いつもの茨城トヨペットにお願いしました。
朝預けて午後2時過ぎ完了です。

ウォーターポンプ交換(作業の方が撮影)


取り外したオルタネータ、意外にきれいでした。

取り外したテンションプーリ

取り外したウォーターポンプ

取り外したアイドラプーリ

取り外したもの

もう一つ交換しました、
パワーステアリングタンク接合部に油が滲んでいたため
パワーステアリングポンプリターンホースの交換をしました。

交換後の写真は場所が狭く、うまく撮影できませんでした。
交換後のオルタネータ

交換後の各プーリ



交換後、アイドリングでも音が静かになりました。
10万キロを越してから、ハブベアリングを交換し、
今回オルタネータ他交換で一区切りです。
残り免許返納まで大丈夫でしょう。
キューキューというような音がするようになりました。
数十秒すると消え、朝のみ、その後音はしません。
おそらく、テンションプーリのゆるみでVベルトから、
または、各プーリからの音と思われます。

対策として、テンションプーリとアイドラプーリのみの
交換しようと思っていましたが、
走行距離11万キロ、サブバッテリーの充電で通常より、
過度に使用していたオルタネータの交換も今回することにしました、
新品は高価なので約半額のリビルト品を使用、
ついでにウォーターポンプも交換です。
今回交換した物
オルタネータ(AL)リビルト品、ウォーターポンプ(WP)、
テンションプーリ(TP)、アイドラプーリ(IP)2個、Vベルト

いつもの茨城トヨペットにお願いしました。
朝預けて午後2時過ぎ完了です。

ウォーターポンプ交換(作業の方が撮影)
取り外したオルタネータ、意外にきれいでした。

取り外したテンションプーリ

取り外したウォーターポンプ

取り外したアイドラプーリ

取り外したもの

もう一つ交換しました、
パワーステアリングタンク接合部に油が滲んでいたため
パワーステアリングポンプリターンホースの交換をしました。

交換後の写真は場所が狭く、うまく撮影できませんでした。
交換後のオルタネータ

交換後の各プーリ



交換後、アイドリングでも音が静かになりました。
10万キロを越してから、ハブベアリングを交換し、
今回オルタネータ他交換で一区切りです。
残り免許返納まで大丈夫でしょう。
2025年03月02日
ポータブル電源リコール
ECOFLOのポータブル電源EFDELTAが個別の異常発煙・発火事象の
発生によりリコールされました。
三元素リチウムイオン電池を使用していたためだと思います。
EFDELTAに関するお詫びと自主回収・交換プログラムのお知らせ
https://www.ecoflow.com/jp/efdelta-recall-and-replacement
我が家も2020年12月に購入、4年使用していました。
https://hide2211.naturum.ne.jp/e3384948.html
当時まだサブバッテリーは鉛だったので、エアコン、電子レンジ等で使用していました。
今回交換品はDELTA2です、こちらは発火リスクが少ない、
リン酸鉄リチウムイオン電池を使用しています。
交換プログラムが提示されすぐに手続きして、
4日後にはDELTA2が配送されました。

左がDELTA2、右がEFDELTA、形状はほぼ同じ、
若干DELTA2の方が高くなっています、



充電端子の位置が側面から100v出力側に変わっています。

仕様を見るとバッテリー容量が1260whから1024whと
236wh少なくなっていました。
DELTA2の仕様

EFDELTAの仕様

追加された機能として、スマホで管理できるようになりました、
バッテリーの状態はもちろん、AC電源等のスイッチを
ON、OFFできるのは非常に助かります。
設置場所がテーブル下のため、のぞき込む必要があり
操作しづらかったためです。



EFDELTAは残量を0%にして、添付された防火シートで包み、
送付された箱に入れます、後日宅配業者が取りに来るそうです。




バロンに設置します、以前と同じ場所テーブルの下です。
乗せる板を置き、上部取手をマジックベルトで固定します。





高くなったので心配しましたが、ギリギリ入りました。

ソーラからの充電、100v出力ケーブルを接続、
テーブルの下に収まりました。



ポータブル電源はサブバッテリーを460Aリチウム化にしたので、
必要ないかもしれませんが、サブバッテリーのサブとして使用しています。
発生によりリコールされました。
三元素リチウムイオン電池を使用していたためだと思います。
EFDELTAに関するお詫びと自主回収・交換プログラムのお知らせ
https://www.ecoflow.com/jp/efdelta-recall-and-replacement
我が家も2020年12月に購入、4年使用していました。
https://hide2211.naturum.ne.jp/e3384948.html
当時まだサブバッテリーは鉛だったので、エアコン、電子レンジ等で使用していました。
今回交換品はDELTA2です、こちらは発火リスクが少ない、
リン酸鉄リチウムイオン電池を使用しています。
交換プログラムが提示されすぐに手続きして、
4日後にはDELTA2が配送されました。

左がDELTA2、右がEFDELTA、形状はほぼ同じ、
若干DELTA2の方が高くなっています、



充電端子の位置が側面から100v出力側に変わっています。

仕様を見るとバッテリー容量が1260whから1024whと
236wh少なくなっていました。
DELTA2の仕様

EFDELTAの仕様

追加された機能として、スマホで管理できるようになりました、
バッテリーの状態はもちろん、AC電源等のスイッチを
ON、OFFできるのは非常に助かります。
設置場所がテーブル下のため、のぞき込む必要があり
操作しづらかったためです。



EFDELTAは残量を0%にして、添付された防火シートで包み、
送付された箱に入れます、後日宅配業者が取りに来るそうです。




バロンに設置します、以前と同じ場所テーブルの下です。
乗せる板を置き、上部取手をマジックベルトで固定します。





高くなったので心配しましたが、ギリギリ入りました。

ソーラからの充電、100v出力ケーブルを接続、
テーブルの下に収まりました。



ポータブル電源はサブバッテリーを460Aリチウム化にしたので、
必要ないかもしれませんが、サブバッテリーのサブとして使用しています。
2025年01月11日
塗装ひび割れの補修
バロンの左右ドア上部(赤丸内)
接合部の塗料のひび割れが目立つようになりました、




この部分、制作当時の写真を見ると、
上部仮装部と下部仮装部をビスで固定、
パテで処理、塗装しています。


ひび割れは納車して2.3年後から発生していましたが、
今までタッチペイントで処理していました、
今回は以前、後部を破損した時の塗料等があるので
しっかり補修しようと思います。
まずは養生して、ひび割れ部にパテを塗ります、
パテが乾いたらサンドペーパーで処理






塗装のための養生をします


塗装はホワイトパールマイカ 下塗り、上塗り、クリアを使用、
今回は小さい塗装なのでぼかしは使用しませんでした、

各3回吹き付け塗装しました、
せっかちなので乾燥前に次の吹き付けをしたがるのですが、
前回それで失敗しているので今回はゆっくり行いました。


ほぼ分からなくなり、終了です。


接合部の塗料のひび割れが目立つようになりました、




この部分、制作当時の写真を見ると、
上部仮装部と下部仮装部をビスで固定、
パテで処理、塗装しています。


ひび割れは納車して2.3年後から発生していましたが、
今までタッチペイントで処理していました、
今回は以前、後部を破損した時の塗料等があるので
しっかり補修しようと思います。
まずは養生して、ひび割れ部にパテを塗ります、
パテが乾いたらサンドペーパーで処理






塗装のための養生をします


塗装はホワイトパールマイカ 下塗り、上塗り、クリアを使用、
今回は小さい塗装なのでぼかしは使用しませんでした、

各3回吹き付け塗装しました、
せっかちなので乾燥前に次の吹き付けをしたがるのですが、
前回それで失敗しているので今回はゆっくり行いました。


ほぼ分からなくなり、終了です。


2024年12月28日
ハブベアリング交換
我が家のトムバロン早いもので、
走行距離11万キロになろうとしています、
最近、50km以上で走行すると、タイヤの走行音でなく、
ヴォーンヴォーンと波打つような音が、
少し聞こえるようになりました、
ハブベアリングの交換時期かなと思い、確認してもらいましたが、
まだガタはなく大丈夫とのことでした。
いずれ交換しなければと思い、今回時期は早いのですが、
ハブベアリングを交換することにしました。
お願いしたのは茨城トヨペット


タイヤを外し、ブレーキ類も取り外します、



ナックル後部の、4本ボルトを外し
ローターとハブを外します、

取り外したハブとローター、ローターは再利用します、

通常さびで取り外しに苦労するそうですが、
9万キロ弱の時、ローターを交換していたため、
ハブはすんなり外れました。
それでも錆があるのできれいに落としてもらいました。

今回ハブASSYも取り替えます、
事前にハブベアリングは圧入してありました、

古いハブからローターを外し、

新しいハブにローターを取付

ナックルにハブを取付


ブレーキ類を元に戻します、


助手席側も同様に作業



最後にタイヤを取付終了です、

茨城トヨペットには写真撮影等お世話になりました、
邪魔にならないようにしましたが、作業しずらかったと思います、
ありがとうございました。
帰宅時の走行では、気になっていた走行音はなくなりました、
やはりベアリングがそろそろ交換時期だったのでしょうか、
これであと10万キロは大丈夫、
それまでに免許返納になってしまうかもしれませんが‥
今回のブログアップは、今年最後になります、
よいお年をお迎えください。
来年もよろしくお願いいたします。
走行距離11万キロになろうとしています、
最近、50km以上で走行すると、タイヤの走行音でなく、
ヴォーンヴォーンと波打つような音が、
少し聞こえるようになりました、
ハブベアリングの交換時期かなと思い、確認してもらいましたが、
まだガタはなく大丈夫とのことでした。
いずれ交換しなければと思い、今回時期は早いのですが、
ハブベアリングを交換することにしました。
お願いしたのは茨城トヨペット


タイヤを外し、ブレーキ類も取り外します、



ナックル後部の、4本ボルトを外し
ローターとハブを外します、

取り外したハブとローター、ローターは再利用します、

通常さびで取り外しに苦労するそうですが、
9万キロ弱の時、ローターを交換していたため、
ハブはすんなり外れました。
それでも錆があるのできれいに落としてもらいました。

今回ハブASSYも取り替えます、
事前にハブベアリングは圧入してありました、

古いハブからローターを外し、

新しいハブにローターを取付

ナックルにハブを取付


ブレーキ類を元に戻します、


助手席側も同様に作業



最後にタイヤを取付終了です、

茨城トヨペットには写真撮影等お世話になりました、
邪魔にならないようにしましたが、作業しずらかったと思います、
ありがとうございました。
帰宅時の走行では、気になっていた走行音はなくなりました、
やはりベアリングがそろそろ交換時期だったのでしょうか、
これであと10万キロは大丈夫、
それまでに免許返納になってしまうかもしれませんが‥
今回のブログアップは、今年最後になります、
よいお年をお迎えください。
来年もよろしくお願いいたします。
2024年11月04日
Kさんバロン、リチウム化工事
栃木Kさんバロンのリチウム化工事に行ってきました。

10月の喜多の郷でお会いした時、リチウム化を希望、
1週間もしない内、リチウムバッテリー、走行充電器、
その他材料を購入しましたと連絡が‥
なんと早いこと。日程調整して伺うことにしました。

10月に喜多の郷で撮影したバッテリー室(鉛バッテリー100A2個)


ソーラコントローラ部

到着して確認すると、すでに鉛バッテリーは取り外し、
バッテリーモニターの取付、BM-2と共にバッテリー室まで配線済でした、
また、写真はありませんが、ソーラコントローラを取り外し、
横にあるスイッチを取り付け直し、
ソーラ配線を開閉できるようにしてありました。
びっくりです、さすが職人さんです、
この後の工事もほとんどKさんが実施、私は口だけでした。

まずはバッテリーを置くスペース確保、

RENOGY50A走行充電器、ヒューズ、開閉器、シャント抵抗器取付

写真がぼけてますが、走行充電器取付、
メインバッテリーから元々リレー経由を経由、
ヒューズ、手動開閉器を取付
リチウムバッテリーは低温保護がないので0℃以下は
開閉器で手動切断できるようにしました。

シャント抵抗器は木材を加工してこの位置に

リチウムバッテリーはLiTime 12V 460Ahを取付、
ベルトで固定配線しました。


この状態で、負荷機器の動作試験、
ソーラ、走行充電の動作確認をしました。

この後の、BM-2取付、100V充電器取付(配線済)、
配線を奇麗にまとめる、FFヒーター配管の再取り付けは、
Kさんが実施するとのこと、今回はこの状態で一旦終了です。
Kさんの準備、作業が良かったので、
当初1日では終わらないと思っていましたが、
3時過ぎには終わりました。
我が家はこの後、道の駅たかねざわ元気あっぷむらで
入浴、車中泊、翌日、道の駅で買い物をして帰宅しました。



10月の喜多の郷でお会いした時、リチウム化を希望、
1週間もしない内、リチウムバッテリー、走行充電器、
その他材料を購入しましたと連絡が‥
なんと早いこと。日程調整して伺うことにしました。

10月に喜多の郷で撮影したバッテリー室(鉛バッテリー100A2個)


ソーラコントローラ部

到着して確認すると、すでに鉛バッテリーは取り外し、
バッテリーモニターの取付、BM-2と共にバッテリー室まで配線済でした、
また、写真はありませんが、ソーラコントローラを取り外し、
横にあるスイッチを取り付け直し、
ソーラ配線を開閉できるようにしてありました。
びっくりです、さすが職人さんです、
この後の工事もほとんどKさんが実施、私は口だけでした。

まずはバッテリーを置くスペース確保、

RENOGY50A走行充電器、ヒューズ、開閉器、シャント抵抗器取付

写真がぼけてますが、走行充電器取付、
メインバッテリーから元々リレー経由を経由、
ヒューズ、手動開閉器を取付
リチウムバッテリーは低温保護がないので0℃以下は
開閉器で手動切断できるようにしました。

シャント抵抗器は木材を加工してこの位置に

リチウムバッテリーはLiTime 12V 460Ahを取付、
ベルトで固定配線しました。


この状態で、負荷機器の動作試験、
ソーラ、走行充電の動作確認をしました。

この後の、BM-2取付、100V充電器取付(配線済)、
配線を奇麗にまとめる、FFヒーター配管の再取り付けは、
Kさんが実施するとのこと、今回はこの状態で一旦終了です。
Kさんの準備、作業が良かったので、
当初1日では終わらないと思っていましたが、
3時過ぎには終わりました。
我が家はこの後、道の駅たかねざわ元気あっぷむらで
入浴、車中泊、翌日、道の駅で買い物をして帰宅しました。


2024年10月27日
ショックアブソーバー他交換
お願いしたのは土浦市の山本自動車


前回、2018年ショック交換して、
6年経過、約6万キロ走行しました、
https://hide2211.naturum.ne.jp/e3100931.html
そろそろ交換しなければと思いつつ、月日が経ってしまいました、
取付てあるオーリンズショックアブソーバーは
オーバーホールができます、
この場合、取外しとオーバーホール後の取付が生じ
工賃が2倍かかります、
今回、KYB、クスコのショックにしようか迷いましたが、
新しいオーリンズショックを取り付けることにしました、

予定時間に到着するともう準備してあり、即作業、
手慣れた、丁寧な作業、
バルトナット締め付け後もしっかりマーキング、
安心感があります。




今回はその他にスタビ関係のゴムが劣化していたので
スタビライザーブッシュ、フロントスタビリンク交換


冷却水パワークーラントHVの交換


クーラーガスクリーニング&パワーエアコンプライアンス、
も作業してもらいました。
ガスは100g少なかったようです、



取り外したショック
フロントはダストブーツが切れていました



取り外したスタビリンク

ショックはしっかり梱包し、次回交換時、
オーバーホールするようにしたいと思います。


動画も撮影しましたが、モザイク等の編集ができず、
今回は掲載出ません。
尚、山本自動車のホームページは下記のとおりです。
https://e-carsearch.net/yamamoto-net/index.asp


前回、2018年ショック交換して、
6年経過、約6万キロ走行しました、
https://hide2211.naturum.ne.jp/e3100931.html
そろそろ交換しなければと思いつつ、月日が経ってしまいました、
取付てあるオーリンズショックアブソーバーは
オーバーホールができます、
この場合、取外しとオーバーホール後の取付が生じ
工賃が2倍かかります、
今回、KYB、クスコのショックにしようか迷いましたが、
新しいオーリンズショックを取り付けることにしました、

予定時間に到着するともう準備してあり、即作業、
手慣れた、丁寧な作業、
バルトナット締め付け後もしっかりマーキング、
安心感があります。




今回はその他にスタビ関係のゴムが劣化していたので
スタビライザーブッシュ、フロントスタビリンク交換


冷却水パワークーラントHVの交換


クーラーガスクリーニング&パワーエアコンプライアンス、
も作業してもらいました。
ガスは100g少なかったようです、



取り外したショック
フロントはダストブーツが切れていました



取り外したスタビリンク

ショックはしっかり梱包し、次回交換時、
オーバーホールするようにしたいと思います。


動画も撮影しましたが、モザイク等の編集ができず、
今回は掲載出ません。
尚、山本自動車のホームページは下記のとおりです。
https://e-carsearch.net/yamamoto-net/index.asp
2024年09月28日
MAXFANギアボックス破損
先日、買い物を兼ね、近くの道の駅水の郷さわらに向かいました。
当日は強風で、一般道走行でも少しハンドルを取られるほどでした。
もう少しで到着、信号待ちしているとき、後ろの方で、
バキという大きな音がしました、追突されたのかと一瞬思いましたが、
そうではありません、相方に後ろの方を確認してもらうと、
MAXFANが閉まらないとのこと、近くのコンビニ駐車場で確認すると、
ギアボックスが粉々に壊れています。

仕方なく、持っている紐とゴムバンドで開かないよう固定、
仮処置をして、帰宅後改修することにしました。


壊れた原因は、強風によるものです、ちょうど後部からの強風でした、
おそらくMAXFANカバーがしっかりしまっていなかったことで、
カバーが少し開いていたかもしれません、
ギアボックスは、2023.12月に交換したばかりです、
MAXFANのコーキング打ち直しとギアボックス交換
https://hide2211.naturum.ne.jp/e3567660.html
帰宅後、保管してあったギアボックスに交換しました。




壊れたギアボックス、粉々です。

当日は強風で、一般道走行でも少しハンドルを取られるほどでした。
もう少しで到着、信号待ちしているとき、後ろの方で、
バキという大きな音がしました、追突されたのかと一瞬思いましたが、
そうではありません、相方に後ろの方を確認してもらうと、
MAXFANが閉まらないとのこと、近くのコンビニ駐車場で確認すると、
ギアボックスが粉々に壊れています。

仕方なく、持っている紐とゴムバンドで開かないよう固定、
仮処置をして、帰宅後改修することにしました。


壊れた原因は、強風によるものです、ちょうど後部からの強風でした、
おそらくMAXFANカバーがしっかりしまっていなかったことで、
カバーが少し開いていたかもしれません、
ギアボックスは、2023.12月に交換したばかりです、
MAXFANのコーキング打ち直しとギアボックス交換
https://hide2211.naturum.ne.jp/e3567660.html
帰宅後、保管してあったギアボックスに交換しました。




壊れたギアボックス、粉々です。

2024年09月22日
メインバッテリーソーラ充電
7月にメインバッテリー100v補完充電のため、
充電端子取付を行い、充電していました。
https://hide2211.naturum.ne.jp/e3594122.html
これが外部電源をつないだり、結構面倒でした。
今回、ソーラから充電する方法にしました。
我が家は通常ソーラからサブバッテリー(リチウム)に充電していますが、
帰宅後のカーポート駐車時は切断しています。
これは過充電防止と100%充電しない方法をとっているからです。
そこで、遊んでいるソーラを利用することに、
鉛バッテリーで使用していたソーラコントローラを利用します、
1年以上屋根裏に放置しておいたので動作するか心配です、
取付前に配線しておきます、


その他開閉器(NFB)、ヒューズ付配線を用意

取付場所は座席下、奥の扉の裏側にしました、
開閉器(NFB)は、メインバッテリー、ソーラから+線を
それぞれON、OFFするように配線しました。

仮接続後、動作確認、曇天だったので、13.4v 1.5A程度でした、


ちなみにカーポートはスモークではありません、

しかし、扉の開閉時、開閉器とコントローラの間の配線が
引っ張られたり、押し込んだりしてしまいます、

配線が動かないよう取付位置変更することに、
既設の配線等を少し動かしスペースを確保、
L型金具と木材で取付ました、




手前の扉を開ければ開閉器の操作、コントローラの動作確認ができます、

後からいろいろなものを取り付けていくと
バッテリー室は配線でごちゃごちゃです、


帰宅後はソーラからのサブバッテリー開閉器を切断、
メインバッテリーの開閉器を入れ、補充電するようにします。


今回は家にある物を使用、開閉器(NFB)のみ購入しました。
充電端子取付を行い、充電していました。
https://hide2211.naturum.ne.jp/e3594122.html
これが外部電源をつないだり、結構面倒でした。
今回、ソーラから充電する方法にしました。
我が家は通常ソーラからサブバッテリー(リチウム)に充電していますが、
帰宅後のカーポート駐車時は切断しています。
これは過充電防止と100%充電しない方法をとっているからです。
そこで、遊んでいるソーラを利用することに、
鉛バッテリーで使用していたソーラコントローラを利用します、
1年以上屋根裏に放置しておいたので動作するか心配です、
取付前に配線しておきます、


その他開閉器(NFB)、ヒューズ付配線を用意

取付場所は座席下、奥の扉の裏側にしました、
開閉器(NFB)は、メインバッテリー、ソーラから+線を
それぞれON、OFFするように配線しました。

仮接続後、動作確認、曇天だったので、13.4v 1.5A程度でした、


ちなみにカーポートはスモークではありません、

しかし、扉の開閉時、開閉器とコントローラの間の配線が
引っ張られたり、押し込んだりしてしまいます、

配線が動かないよう取付位置変更することに、
既設の配線等を少し動かしスペースを確保、
L型金具と木材で取付ました、




手前の扉を開ければ開閉器の操作、コントローラの動作確認ができます、

後からいろいろなものを取り付けていくと
バッテリー室は配線でごちゃごちゃです、


帰宅後はソーラからのサブバッテリー開閉器を切断、
メインバッテリーの開閉器を入れ、補充電するようにします。


今回は家にある物を使用、開閉器(NFB)のみ購入しました。